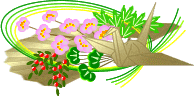
月刊OTANI'11 新年号特別企画 2
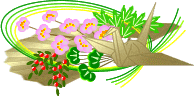
月刊OTANI'11 新年号特別企画 2
![]()
年始に食べるおせち料理は、次第に「自宅で作る」から「セットで買う」に移りつつあると聞きます。地方によってそれほど違いがあるようには思えませんが、それでもそれぞれの地域やご家庭で、お母さんやおばあちゃんの作るおせち料理には、お一人おひとりの思い入れや思い出があるのではないでしょうか。
比較的年長の社員の方々に「おせちの味」にまつわる思い出、家族のエピソードを、お話いただきました。
![]()
大晦日の台所は母の領域
業務部製品発送課 村上正男
私の子供のころの年末年始風景といえば、まず思い浮かぶのは、大晦日の母の姿です。
この日は、朝から母が台所に立ち、お正月に食べるおせちの支度に取り掛かっていました。
当時は「練炭火鉢」が威力を発揮して、煮しめや黒豆などをコトコト時間をかけて煮込むのに役立っていました。家中に煮物の香りが広がっていました。
母はあまりからだが強いほうではなかったですが、この日の台所は、文字通り「母の領域」で、誰も立ち入らせない雰囲気がただよっていました。夕方には、一日がかりで作った、伊達巻、紅白かまぼこ、かずのこ、酢だこ、真鱈の子の煮物などが並び、新年を待つばかりになっていました。当時には普段あまり食卓に上らないものも多く、子供心に新年が待ち遠しかったものです。
元旦には、みんなそろった食卓に大きな器に入ったおせち料理が並び、「明けましておめでとうございます」の挨拶と同時に、いただきました。ちょっとしょっぱめの味付けは、父のお酒のおつまみにぴったりだったようで、うれしそうに杯を重ねていました。テレビを見ながら家族そろってゆったりと食べる風景は、お正月ならではだったと思います。
今の我が家はすべて手作りではなく、店で買ってきたオードブルなども並びますが、それでも妻と娘でおせちを作ってくれます。もちろん練炭火鉢ではなく、ガスや電気、圧力鍋等でつくっています。妻の作るおせちの味を子供たちに受け継いでほしいと思います。
父の代からの杵と臼
我が家のもうひとつの年末の風景は「餅つき」。子供のころから年末恒例行事として欠かせなかったです。今も毎年30日に一日がかりで、私の家と近所のもう一軒と合同で、餅つきをします。杵と臼は父親の代から受け継がれているもの。7〜8臼つきますが、杵はもう一軒の息子にまかせ、今はもう私はもっぱら「手水担当」に徹しています。
ついた餅はだいたい“伸し餅”にして、翌日に切って近所に配って喜ばれています。特にお年寄りには、豆餅、こぶ餅が喜ばれています。私は以前、和菓子職人だったこともあり、餅作りについてはこだわりがあります。粘り気を出すために、手水はぬるま湯にしたり、塩を入れて割れを防いだり。
買えば済むようですが、家族みんなの行事は、地域の方たちとも交流できる良い機会です。地域行事でも餅つきをしていると、近所の高校生が興味をもってくれたらしく、毎年来てくれます。杵を渡してやってもらい、うまくつけない子には教えてあげる。こうした交流を通じて、子どもたちも将来餅つきを続けてくれたらと思います。

![]()
農家育ちの母のこだわりおせち
技術部電気課 宮永博孝
母は農家育ちだったので、母が作るおせちは、筑前煮、三杯漬け、黒豆など、野菜ものが中心でした。
富山ではよく、「煮しめ」と言うそうですが、私が生まれ育った福岡では「筑前煮」と言って、小芋、れんこん、こんにゃく、骨付きのかしわ、にんじんなどを薄味で炊いたものを普段からも良く食べました。
三杯漬けとは、かぶ、にんじん、細切り昆布を和えて三杯酢で漬けたもののこと。味は京都のお漬物の「千枚漬け」に近いです。かぶは短冊切り、にんじんも花型にくりぬかれていて、母のこだわりの料理ではなかったかと思います。
富山のかまぼこは赤巻きや昆布巻きなどが主流ですが、私の家ではもっぱら板付きのかまぼこです。巻きかまぼこは、富山に来てから初めて見ました。
富山に来てから、お正月の習慣も所々違うということに気付きました。私の家では元日に朝風呂に入ります。福岡で子供の頃は、元旦の銭湯は満員でした。地域によっては元日にはお風呂に入らないという風習もあるようです。
福岡の餅つきは足踏み式
母は10人兄弟で、私が子供の頃、年末には母の実家に親戚一同が集まり、とにかく大所帯でにぎやかでした。親戚が集まると、杵と臼で餅つきをしました。実家では、餅つき風景も富山とは少し様子が違います。杵は手で振り下ろすのではなく、柄の中央付近を支点にして片方を足で踏みながらシーソーのようにつきます。つきたての餅は、中にあんこをいれて丸めて食べますが、あつあつの餅をちぎるのは母の仕事、餅の中にあんこをいれて丸めるのは子供たちの仕事でした。それ以外には、伸し餅にして切って、お雑煮にも入れました。
その後、長年神戸に移り住みました。子供が生まれてからは、子供が好きなエビ、唐揚げやハムなどが盛り付けられたオードブル風のおせちが主流となりましたが、妻は昔ながらのおせちも作ってくれます。かずのこ、鯛の塩焼き、鰤の照り焼きなどですが、私の好物はなまこ酢です。おせちはもともと正月に女性が料理しなくてもいいように、作りおきできる食材が主だったと思いますが、最近は子供も居るので、正月の夜は鍋を囲むのが定番になっています。
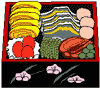
![]()
普段の食材でも華やかさを演出
総務部総務課 柳浦敏文
わたしは昭和30年代半ばころに幼・少年時代をすごしました。高度経済成長が始まるまでのこの時代、まだまだ、もの不足の感が否めず、普段食べる食材も、今の時代に比べると種類も調理法もうんと少なかったように思います。
私の家は氷見市で、父が魚の仲買をしていたので、さいわい魚には恵まれていました。普段から新鮮なお魚が手に入っていたので、お刺身や魚の煮つけなどは、特別な料理というイメージはありません。食材で特別なおせち料理はなかったように思います。
それでも、お正月おせち料理となると、まず思い出すのは「大根なます」と「紅白のかまぼこ」です。普段と変わらない煮物や豆と並んで、両方とも特別なものではないのに、大根なますは大根とにんじんの「紅白」、かまぼこも富山県ならではの巻きかまぼこで、赤、白、昆布を交互に並べることで、一度に「華やかさ」を感じたものです。
世の中がまだ、けっして豊かと言えない時代でした。ご飯を炊くのはかまど、日常使う水は井戸からのくみ上げ水。みかんの木箱買いなどもままならない時代です。母がせめてお正月らしいにぎやかさを工夫したのが、この品だったと思います。
甘いけれど苦い思い出
当時の我が家のお正月に、もうひとつ欠かせないものは、年末28日におこなう家族恒例の餅つきです。子供心に、年に一度の一大イベントであり、普段なかなか口にできないお餅がふんだんに食べられる機会として楽しみにしていました。お正月のお雑煮として食べる伸し餅と、薄く切って藁(わら)で編んで天井からつるして乾かす「凍(こお)り餅」として食べるのですが、子供たちは乾く前から、棒で落として食べるのを楽しみにしていました。炬燵(こたつ)の炭火で焼くか、どの家にもあった練炭火鉢で焼いて食べます。貴重なおやつでしたね。
お正月の「甘いけれど苦い思い出」が「干し柿」です。普段はなかなか食べる機会がない干し柿が、鏡餅のお飾りに乗っているのを、我慢できなくなって食べてしまって親にこっぴどく叱られたのも、今となれば“たのしい”思い出です。
この時代に比べれば、今はちょっとした“おせちセット”でも、ローストビーフやローストチキン、栗きんとんなど、豪華さを競っています。それでも、私にとっての“おせち”の思い出はやはり母親の作ってくれた煮物、黒豆、大根なますなどです。
![]()
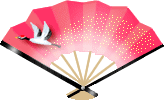
■各ページへのリンク■
【平成23年度 フレッッシュ社員座談会】
【我が家の“おせち”の味】
【「花を撮る」写真サークル撮影旅行記】
【編集後記】
【INDEX】
※月刊「OTANI」へのご意見・ご感想は
メール ・ ご意見板
※メールの件名は変更せず
そのまま送信してください。
![]()